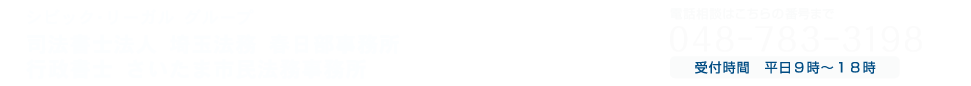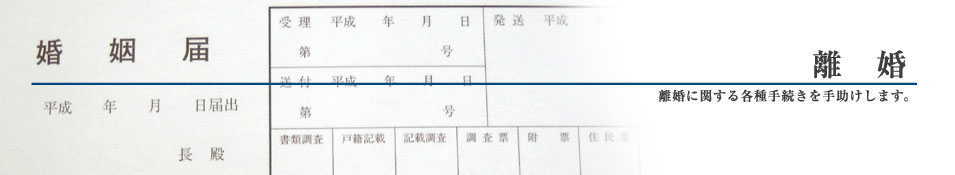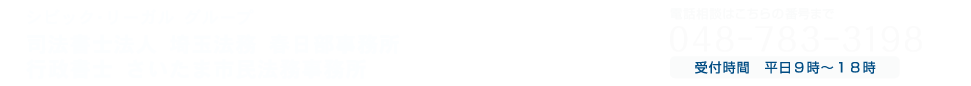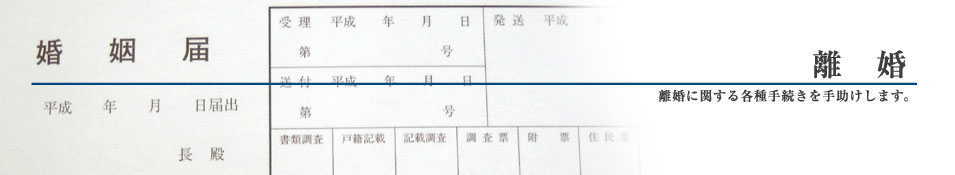司法書士 行政書士
春日部市民法務事務所
|
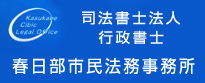 |
 |
| 所在地 |
【春日部オフィス】
〒344-0065
春日部市谷原2-7-8
サンヴェール春日部111
【さいたま大宮オフィス】
〒330-0841
埼玉県さいたま市大宮区
東町1-117 大宮ATビル304
|
 |
営業時間
平日 9:00~18:00
※時間外、土・日・祝日の相談も可能です。お気軽にご相談ください。 |
 |
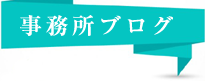 |
|
|
| 離婚協議書について |
夫婦間で離婚をすることに関して合意をしたら、離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。
しかしながら、離婚が成立したら、夫婦間で決めなければならないことがいくつかあります。
それは、「慰謝料」「財産分与」「年金分割」、
子供がいる場合には、「親権者をどちらにするか」「養育費」、
マイホームを購入している場合には、「住宅ローンをどうするか」「不動産をどちらの名義にするか」などです。
離婚協議の結果、自分が不利な状況に追い込まれ、後に困ることのないように当事務所はしっかりとサポートいたします。
離婚協議書は、必ず公正証書にしておきましょう。
養育費などの支払いが怠った場合、裁判所の判決などを待たないで直ちに強制執行手続きに移ることができます。
慰謝料や養育費の支払を離婚協議書で定めた後、最初はきちんと支払ってくれたのに、すぐに支払わなくなってしまった、というケースは多々あります。そのような状況になった際に、「取り決めた約束を守らなかったら、強制執行をしても構いません」という強制執行認諾条項とよばれる文章を記載した公正証書で離婚協議書を作成していれば、訴えを提起することなく、相手方の給与、その他財産に強制執行をかけて支払いを履行することが出来ます。
それを公正証書化していない場合には、通常、相手方に対して訴えを提起し、勝訴判決をもらった後に差押の手続きをしなければなりません。
この場合には、訴訟を起こすために弁護士をつけることが多く、その為には多額の費用と時間・労力がかかってしまいます。
|
|
離婚の養育費について |
未成年の子供がいる場合、子供を養育する方が、相手に養育費を請求できます。
どれくらいの養育費が良いか、ということですが、特段の規定がないため、協議をして決定します。
養育費の金額は 親の生活水準によって異なり、子供は、従来の生活水準を維持するのにかかる費用を求めることができるため、一般的にいくらということはできません。参考までに、家庭裁判所の調停によって決められた養育費の額は、子供一人につき月額2~4万円のケースが多いようです。
養育費は将来、支払われなくなることも多いため、養育費を払ってもらえなくなった場合に、すぐに相手の給料などを差し押さえできる方法をとっておくべきです。
それが、離婚協議書を「公正証書」で作成することです。
公正証書化していない場合には、通常、相手方に対して訴えを提起し、勝訴判決をもらった後に差押の手続きをしなければならないので、時間も多額な費用もかかることになってしまいます。
|
|
財産分与について |
財産分与とは、婚姻中に形成した財産を清算することです。
財産は、潜在的に夫婦共有財産と考えられ、たとえ名義は一方の配偶者(夫の場合が多い)となっていても他方の協力があってのことであるとされています。
協議離婚の場合、財産分与については口約束だけであやふやになっている場合も多くみられます。
後の紛争を防ぐためには「不動産の名義をどちらにするか」はもちろんのこと、「不動産以外の財産分割」や「養育費」の問題なども含めた財産分与契約書を作成しておくことをお勧めします。
当事務所では、「離婚協議書の公正証書の作成」と「不動産の名義変更手続」を一か所で行え、離婚手続をトータルでサポートさせていただいております。
また、財産分与請求権は、離婚成立の日から2年で時効になってしまうので注意が必要です。
|
|
| » 財産分与の割合は? |
財産分与の割合は、夫婦双方にどれだけ財産分与するかの割合を共有財産・実質的共有財産を明確にし、決定します。
① 夫婦が共働き、または妻も家業に従事している場合は、割合は原則的に財産分与の割合は50%になります。
② 妻の側が専業主婦の場合は特別な事情(財産形成に金銭的に寄与した家計を支えるために大きな尽力があった)といった事情がないかぎり財産分与の割合は50%未満になる場合が多いのが現状です。
|
| » 住宅ローン付き不動産を財産分与する場合は? |
ケース1.妻がローンを引き継ぎ、妻が居住する
ケース2.夫にローンだけを支払ってもらって妻が居住する
ケース3.夫がローンを支払い夫が居住する
ケース4.住宅を売却して残債について債務整理を開始する
のような方法が考えられます。
|
| » ローンなし不動産を分ける場合 |
① 売却して、その金額を分ける
② どちらかが住宅を単独で所有し、相手の持分についてお金を払う
③ 持分を決めて共有とし、不動産分割請求をする。
のような方法が考えられます。 |
|
 |
年金分割について |
| » 合意分割制度とは? |
当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての厚生年金の分割を受けることが出来ます。
離婚時に当事者間の話し合いで分割割合について合意の上、社会保険事務所に厚生年金分割の請求をします。
なお、分割割合は婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分を限度とします。
合意がまとまらない場合、家庭裁判所が分割割合を定めることが出来ます。 |
|
| » 3号分割制度とは? |
被扶養配偶者(第3号被保険者、会社員・サラリーマンの妻)を有する第2号被保険者(厚生年金を会社で天引きされている会社員・サラリーマン)が負担した保険料は、夫婦が共同して負担したものであることを基本的認識としています。
離婚等をした場合、同意がなくともこの期間の第2号被保険者(主に夫)の厚生年金の保険料納付記録は、強制的に2分の1に分割されます。
事実上の婚姻関係(内縁)であっても 第3号被保険者(扶養に入っている人)の方は「婚姻関係にあった」と認められ、分割対象になります。
また、「合意分割」も「3号分割」も、離婚成立の日から2年で時効になってしまうので注意が必要です! |
|
|
|
| ローンなし不動産を分ける場合 |
① 売却して、その金額を分ける
② どちらかが住宅を単独で所有し、相手の持分についてお金を払う
③ 持分を決めて共有とし、不動産分割請求をする。
のような方法が考えられます。 |
|
|
①情報提供の請求
離婚前でも離婚後でも、当事者の2人が共同で行うことも、1人だけで行うことも出来ます。
ただし、一度情報提供の請求をした場合、その後3ケ月を経過していない時は、原則、再請求は出来ません。 |
▼
②当事務所での面談・ヒヤリングによる必要書類のご案内
※委任状に署名捺印いただきます。 ※法人で許可を取る場合は、会社謄本を持参ください。 |
▼
③年金分割の請求
当事者の一方だけで行うことが出来ます。窓口は最寄の社会保険事務所です。
請求後、按分割合に基づいて当事者それぞれの保険料納付記録の改定が行われ、当事者それぞれに改定後の保険料納付記録が通知されます。 |
|
|
|
| 手続きの種類・費用 |
| 項 目 |
報 酬 |
| 離婚のご相談料 |
初回のみ無料
2回目以降 1時間5000円
※離婚協議書作成ご依頼の場合は、相談料は無料です。 |
|
※会社謄本・住民票・納税証明書などを当事務所で代理取得する場合は、別途実費および手数料がかかります。
※必要書類を収集する際の通信費・交通費などの実費は別途かかります。
|
|
|
| 離婚協議書サポートプラン |
| 項 目 |
報 酬 |
①離婚手続のアドバイス
②離婚協議書(公正証書)作成
③公証人との打ち合わせ
④公証役場への同行 |
6万円(税別) |
|
※公証役場の手数料は実費として別途かかります。
目的物の価額が100万円までの場合、作成手数料は5000円
200万円までの場合、作成手数料は7000円
500万円までの場合、作成手数料は11,000円
1000万円までの場合、作成手数料は17,000円
|
|
| 離婚手続き一式サポートプラン(不動産名義変更あり) |
| 項 目 |
報 酬 |
①離婚手続のアドバイス
②不動産調査
③住宅ローンについてのアドバイス
④離婚協議書(公正証書)作成
⑤公証人との打ち合わせ
⑥公証役場への同行
⑦不動産名義変更登記 |
15万円(税別) |
|
※公証役場の手数料、登録免許税、不動産登記簿謄本、郵送料などの実費は別途かかります。
|
|
 |
▼
▼
➂公正証書の原案作成
(内容の追加や修正、ご質問等がある場合は、お気軽にお電話下さい。)
※離婚することの合意、公正証書を作成することの合意、
公正証書の内容についてのおおすじでの合意が成立していることが必要です。 |
▼
④公正証書の原案を、夫婦双方にご確認いただきます。
(この時点での、追加や修正は可能です) |
▼
▼
▼
⑦公証役場にて公正証書の作成
※公証人の手数料は、当日直接公認役場へお支払ください。
基本的には、夫婦双方にお越しいただくことをお願いしていますが、
無理な場合は、代理人を立てることもできます。
※当日は当職も立ち会います。
|
|
 |